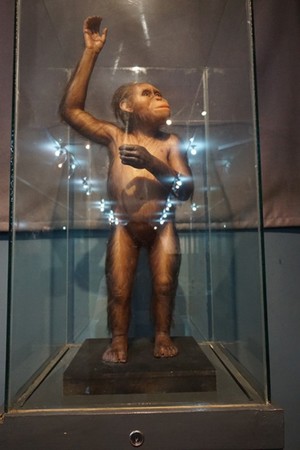ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載しています。
今回から全6回で、ロシアによるウクライナ侵攻について書いたものを掲載します。第1回は歴史家ティモシー・スナイダーの『自由なき世界 フェイクデモクラシーと新たなファシズム』(翻訳:池田年穂/慶応義塾大学出版会)の紹介です。(公開は2022年4月7日。一部改変)
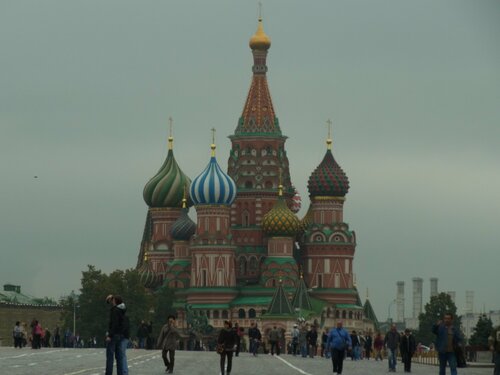
******************************************************************************************
プーチンによるウクライナへの全面侵攻を予測できた専門家はほとんどいなかったというが、歴史家のティモシー・スナイダーは間違いなく、その数少ない例外の一人に入るだろう。
2014年、ロシアはクリミアを占拠し、ウクライナ東部のドンバス地方に侵攻したが、欧米諸国は限定的な経済制裁に止め、その4年後、ロシアはサッカー・ワールドカップを華々しく開催した。
ヨーロッパ(とりわけドイツ)はロシアにエネルギー供給を依存し、中国の台頭に危機感を募らせたオバマ政権もロシアとの対立を望まなかった。「クリミアはソ連時代の地方行政区の都合でウクライナに所属することになっただけ」「ドンバス地方を占拠したのは民兵でロシア軍は関与していない」などの主張を受け入れ、「ロシアはそんなに悪くない」とすることは、誰にとっても都合がよかったのだ。
だがスナイダーは、2018年の『自由なき世界 フェイクデモクラシーと新たなファシズム』でこうした容認論を強く批判した。プーチンのロシアは「ポストモダンのファシズム(スキゾファシズム)」に変容しつつあるというのだ。
スナイダーは中東欧の11か国語を操る気鋭の歴史家で、語り尽くされたと思われていたホロコーストについて、その本質はアウシュヴィッツのガス室ではなく、ナチス(ヒトラー)とソ連(スターリン)による二重のジェノサイドだという新しい視点を提示して大きな反響を呼んだ。
じつは私は、2020年に本書の翻訳を手に取ったとき、プロローグと第1章までで読むのをやめてしまった。「歴史家としては超一流でも、それで現代の国際政治が語れるのか」と疑問を感じたからだ。
今回のウクライナ侵攻で自らの不明を思い知らされ、あらためて本書を読み直してみた。原題は“The Road to Unfreedom; Russia, Europe, America”(アンフリーダムへの道 ロシア、ヨーロッパ、アメリカ)で、フリードリッヒ・ハイエクの“The Road to Serfdom”(隷属への道)を意識しているのだろう。
ハイエクはこの名高い著作で、ソ連の計画経済は必然的に破綻し「現代の農奴制(Serfdom)」に至ると説いた。それに対してスナイダーは、プーチンが行なっているのは歴史の改竄と国民の洗脳で、そこから必然的に「自由なき世界(Unfreedom)」が到来するのだと予見する。
「ロシア正教ファシズム」の教祖
スナイダーによれば、現代のロシアを理解するうえでもっとも重要な思想家はイヴァン・イリインだという。ロシア以外ではほとんど知られていないこの人物は、1883年に貴族の家に生まれ、当時の知識層(インテリゲンチャ)の若者と同様にロシアの民主化と法の統治を願っていたが、1917年のロシア=ボルシェビキ革命ですべてを失い、国外追放の身となる。その結果、理想主義の若者は筋金入りの反革命主義者になり、ボルシェビキに対抗するには暴力的手段も辞さないという「ロシア正教ファシズム」を提唱するようになった。
イリインは忘れられたまま1954年にスイスで死んだが、その著作は、ソ連崩壊後のロシアで広く読まれるようになり、2005年にはプーチンによってその亡骸がモスクワに改葬された。プーチンは、「過去についての自分にとっての権威はイリインだ」と述べている。
イリインの思想とはなんだろう。それをひと言でいうなら、「無垢なロシア(聖なるロシア)の復活」になる。
イリインの世界観では、宇宙におけるただ一つの善とは「天地創造以前の神の完全性」だ。ところがこの「ただ一つの完全な真理」は、神がこの世界を創造したとき(すなわち神自身の手によって)打ち砕かれてしまった。こうして「歴史的な世界(経験世界)」が始まるのだが、それは最初から欠陥品だったのだ。
イリインによれば、神は天地創造のさいに「官能の邪悪な本性」を解放するという過ちを犯し、その結果、人間は「性に突き動かされる存在」になった。性愛を知りエデンの園を追放されたことで、人間は存在そのものが「悪(イーブル)」になった。だとしたらわたしたちは、個々の人間として存在するのをやめなければならない。
興味深いのは、イリインが1922年から38年までベルリンで精神分析を行なっていたことだ。この奇妙な神学には、明らかにフロイトの影響が見て取れる。
人間が存在として悪だとしても、いかなる思想も自分自身を「絶対悪」として否定することはできない。イリインがこの矛盾から逃れるために夢想したのが、「無垢なロシア」だった。邪悪な革命政権(ソ連)を打倒しロシアが「聖性」と取り戻したとき、世界は(そして自分自身も)神聖なものとして救済されるのだ。
ロシアが悪事をなすわけはなく、ロシアに対してだけ悪事がなされる
イリインは、祖国(ロシア)とは生き物であり、「自然と精神の有機体」であり、「エデンの園にいる現在を持たない動物」だと考えた。細胞が肉体に属するかどうかを決めるのは細胞ではないのだから、ロシアという有機体に誰が属するかは個人が決めることではなかった。こうしてウクライナは、「ウクライナ人」がなにをいおうとも、ロシアという有機体の一部とされた。
極左の無法は、極右のさらに大いなる無法によって凌駕するほかないとするイリインにとって、ファシストのクーデター、すなわち愛国的な独裁政こそが「救済行為」であり、この宇宙に完全性が戻ってくることへの第一歩だった。そして、ロシアが聖性を取り戻すには「騎士道的な犠牲」を果たす救世主が必要で、いずれ一人の男がどこからともなく現われ、ロシア人たちはその男が自分たちの救世主だと気づくだろうと予言した。
イリインが理想とする社会は「コーポレートの構造(cooperate structure)」で、国家と国民とのあいだに区別はなく、「国民と有機的かつ精神的に結合する政府と、政府と有機的かつ精神的に結合する国民」があるだけだ。
キリスト教(ロシア正教)ファシズムの社会では、国民は個人の理性を捨てて国家(有機体)への服従を選ばなくてはならない。有権者がすべきことは政権の選択ではなく、「神に対し、この人間界に戻ってきてロシアがあらゆる地で歴史を終わらせるのを助けてくれるよう乞うこと」だけだ。
こうしてイリインは、「ロシア人に自由選挙で投票させるのは、胎児に自らの人種を選ばせるようなものだ」として民主政を否定する。選挙は独裁者に従属の意思表示をし、国民を団結させる儀式でしかなく、投票は公開かつ記名で行なわれるべきだというのだ。
イリインが唱えたのは「永遠に無垢なるロシア」という夢物語であり、「永遠に無垢なる救世主」という夢物語だ。こうして(仮想の)ロシアを神聖視してしまえば、現実世界で起きることはすべて「無垢なロシアに対する外の世界からの攻撃」か、もしくは「外からの脅威に対するロシアの正当な反応」でしかなくなる。
イリイン的な世界では、「ロシアが悪事をなすわけはなく、ロシアに対してだけ悪事がなされるのだ。事実は重要ではないのだし、責任も消えてなくなってしまう」とスナーダーはいう。
ロシアはファシズムによって世界を救う
イリインの神学がソ連崩壊後のロシアで広く受け入れられたのは、それが(ソ連国民が徹底的に教育された)マルクス主義、レーニン主義、スターリン主義と「気味の悪いほど似通っていた」からだ。両者が哲学的起源として共有するのがヘーゲル哲学だった。
ヘーゲルは、「「精神(スピリット)」と呼ばれる何か、すなわちあらゆる思考と心を統一したものが、時代を特徴づける種々の衝突を通して発現する」と論じた。その哲学によれば、カタストロフは進歩の兆しであり、「もし「精神」が唯一の善であるならば、その実現のために歴史が選ぶいかなる手段もまた善である」。
マルクスをはじめとするヘーゲル左派は、ヘーゲルが神を「精神」という見出しを付けてその思想体系にこっそり持ちこんだのだと批判した。マルクスにとって絶対善は「神」ではなく「人間の失われた本質」であり、歴史は闘いではあるが、その目的は人間がその本質を取り戻すことだった。
それに対してイリインなどのヘーゲル右派は、ヘーゲルがいったんは自身の哲学から隠蔽した神を堂々と復活させた。ひとびとが苦しむのは、「資本家」が「労働者」を抑圧するからではなく、神が創造した世界が手に負えないほど矛盾に満ちたものだからだ。だからこそ、選ばれた国家が救世主の起こす奇跡によって「神の完全性」を復活させなければならないし、その高尚な目的のためにはどのような手段も正当化される。
レーニンは、「前衛党(教育を受けたエリート)」には歴史を前に進める権利があると信じていた。「この世界で唯一の善が人間の本質を取り戻すことなのだとしたら、その手順を理解している者がその達成を早めるのは当然のこと」なのだ。
それに対してイリインは、「神の完全性」という究極の目的を実現するためには、暴力的な革命(より正確には暴力的な「反革命」)を受け入れるのは当然だとした。ロシアはファシズムから世界を救うのではなく、ファシズムによって世界を救うのだ。
革命直後のレーニンらは、「自然が科学技術の発展を可能にし、科学技術が社会変革をもたらし、社会変革が革命を引き起こし、革命がユートピアを実現する」という科学的救済思想を唱えた。だがブレジネフの時代(1970年代)なると、欧米の自由主義経済に大きな差をつけられたソ連は、こうした救済の物語を維持するのが困難になってきた。
ユートピアが消えたとしたら、そのあとの空白は郷愁の念で埋めるしかない。その結果ソ連の教育は、「よりよい未来」について語るのではなく、第二次世界大戦(大祖国戦争)を歴史の最高到達点として、両親や祖父母たちの偉業を振り返るように指導するものに変わった。革命の物語が未来の必然性についてのものだとすれば、戦争の記憶は永遠の過去についてのものだ。この過去は、汚れなき犠牲でなければならなかった。
この新しい世界観では、ソ連にとっての永遠の敵は退廃的な西側文化になった。1960年代と70年代に生まれたソ連市民は、「西側を「終わりなき脅威」とする過去への崇拝(カルト)のなかで育っていた」のだ。
マルクス・レーニン主義とイリインの思想は合わせ鏡のような関係で、だからこそロシアのひとびとは、ソ連解体後の混乱のなかで、救世思想のこの新たなバージョンを抵抗なく受け入れることができたのだ。
モンゴルの支配が「聖なるロシア」を生んだ
イリインのキリスト教(ロシア正教)ファシズムと並んでプーチンのロシアで大きな影響力をもつようになったのが、神秘思想家レフ・グミリョフ(1912-1992)の「ユーラシア主義」だ。
ナポレオンのロシア遠征によって近代の衝撃を受けたロシアでは、「スラブ主義(ロシア的共同体)」と「ヨーロッパ化主義(自由とデモクラシー)」の論争が飽きることなく繰り返された。だが初期のユーラシア主義はこのいずれの立場も拒絶し、西欧文化に対するロシアの優越を「モンゴルによる統治」に求めた。
1240年代初め、モンゴル人はルーシの残党をいとも簡単に打ち負かした。一般には「タタールのくびき(モンゴル支配)」はロシアの歴史における屈辱と見なされているが、ユーラシア主義者はこれを逆転させて、「モンゴルによる統治という幸運な慣習」のおかげで、ルネサンス、宗教改革、啓蒙思想などといったヨーロッパの腐敗とは無縁の環境で、新たな都市モスクワを創ることができたのだと主張した。ロシアがキリスト教世界のなかで特別な存在なのは、「タタールのくびき」によって、西欧文明に毒されることなく「無垢な精神=聖なるロシア」を保ってきたからなのだ。
詩人の両親のもとに生まれたグミリョフは、9歳のときに父親がチェカー(秘密警察)に処刑され、自らもスターリン治下の大粛清で、1938年から5年間、1949年から10年間を強制収容所で過ごすことになった。
グミリョフはこの過酷な監禁生活のなかで、「抑圧のなかに閃きの兆を見出し、極限状況においてこそ人が生きるうえでの本質的な真実が明らかにされる」と信じた。ユーラシア主義に傾倒したグミリョフは、「モンゴル人こそロシア人がロシア人たる所以であり、西側の退廃からの避難所である」とし、ユーラシアとは、「太平洋岸から、西端の無意味で病んだヨーロッパ「半島」にまで伸びてゆく、誇るべきハートランド」だと考えるようになった。
グミリョフの神秘思想では、人間の社会性は「宇宙線」によって生まれ、それぞれの民族の起源を遡れば、宇宙エネルギーの大放出にまで辿り着く。西側諸国を活性化させた宇宙線ははるか昔に放たれたため、いまや西欧は没落の途上にあるが、ロシア民族はキプチャク・ハン国軍を破った「クリコヴォの戦い」(1380年9月8日)に放出された宇宙線によって生まれたので、いまだ若く生命力に満ちあふれている。
グミリョフによれば、すべての「健康な」民族は宇宙線から誕生したが、なかには他の民族から生命を吸いとる「キメラ(ライオンの頭,ヤギの胴,ヘビの尾をもつギリシア神話の怪物)のような集団」もいる。この集団とはユダヤ人のことで、「ルーシの歴史とは、ユダヤ人が永遠の脅威であることを示すものだ」という強固な反ユダヤ主義を唱えた。
わたしたちはみな、生命体として宇宙エネルギーの影響を受けているが、まれにこの宇宙エネルギーを大量に吸収し、それを他者に分け与えることができる者がいる。これが「パッシオナールノスチ」で、この特別な能力をもつ指導者こそが民族集団を創る。
イリインのいう「無垢なるロシアを復活させる独裁者」と、グミリョフの「パッシオナールノスチを有する指導者」は、その後、アレクサンドル・ドゥーギンによってウラジミール・プーチンという一人の政治家に重ね合わされることになる。
ロシアは「運命の男」に統治されねばならない
1962年生まれのアレクサンドル・ドゥーギンは、1970年代と80年代にはソヴィエトの反体制派の若者として、ギターを弾き、「何百万人もの人間を「オーブン」で焼き殺す歌を歌っていた」とされる。
ソ連崩壊後の1990年代初め、ドゥーギンはフランスの陰謀理論家ジャン・パルヴュレスコと親しくなった。パルヴュレスコにとって歴史とは「海の民(大西洋主義者)」と「陸の民(ユーラシア主義者)」との闘いで、「アメリカ人やイギリス人は海洋経済に従事することで、地に足の着いた人間の経験から切り離されたがために、ユダヤ人の抽象的な発想に屈してしまう」のだと論じた。フランスのネオ・ファシスト運動の提唱者アラン・ド・ブノワも、「アメリカが抽象的な(ユダヤ的な)文化の代表としてこうした陰謀の中心的な役割を果たしている」とドゥーギンに説いた。
1993年、ナチスの思想を母国ロシアに持ち帰ったドゥーギンは、エドワルド・リモノフと共同で「国家ボルシェビキ党」を設立、97年には「国境のない赤いファシズム」を呼びかけた。ドゥーギンはここで、「民主主義は空疎である。中流階級は悪である。ロシアは「運命の男」に統治されねばならない。アメリカは邪悪である。そしてロシアは無垢なのだ……」という「月並みなファシストの見方」を披露した。
ドゥーギンにとって西欧は「ルシファーが堕天した場所」「世界的な資本主義の「オクトパス」の中心」「腐った文化的堕落と邪悪、詐欺と冷笑、暴力と偽善の温床(マトリックス)」だった。さらには、独立したウクライナ国家は「ロシアがユーラシアになる運命を阻む障壁」だとされた。
プーチン政権誕生後の2005年、ドゥーギンは国の支援を受けて、ウクライナ解体とロシア化を訴える青年運動組織「ユーラシア青年連合」を設立し、09年には「クリミアとウクライナ東部を求める戦い」を予見した。ドゥーギンから見れば、ウクライナの存在は「ユーラシア全体にとって大いなる脅威」だった。
さらには、ロシア正教の修道士で、イリインを改葬したティホン・シュフクノフが、ウラジミール・プーチンこそが、ロシア人が「ウラジミール」と呼ぶ古代キエフの王の生まれ変わりだと唱えた。ウクライナではヴォロディーミルまたはヴァルデマーと呼ばれるこのルーシの王こそが、今日のロシア、ベラルーシ、ウクライナの地を永遠に結びつけることになったというのだ。
このようにして、イリインのキリスト教(ロシア正教)全体主義、グミリョフのユーラシア主義、ドゥーギンの「ユーラシア的」ナチズムという3つの思潮が合流し、「ロシア・ファシズム」が誕生したのだ。
世界を救済し、神の完全性を復活させる壮大なプロジェクト
プーチンは、2004年にウクライナのEU加盟を支持し、それが実現すればロシアの経済的利益につながるだろうと述べたと、スナイダーは指摘する。EUの拡大は平和と繁栄の地域をロシア国境にまで広げるものだと語り、08年にはプーチンはNATOの首脳会談に出席している。
ところが同年のジョージア(グルジア)侵攻が欧米から強く批判されると、一転して2010年には「ユーラシア関税同盟」を設立する。これは「リスボンからウラジオストクまで(大西洋岸から太平洋岸まで)広がる調和的な経済共同体」とされたが、その実態は、「EUの加盟国候補になれそうもないとわかった国々を団結させようとした」ものでしかなかった。
12年1月の大統領選挙直前の論説では、プーチンは「ロシアは元々が無垢な「文明」だった」として、ロシアを国家ではなく霊的な状態として説明した。さらにはイリインを引用して、「偉大なロシアの任務は、文明を統一し結びつけることである。このような「国家=文明」には民族的少数者など存在しないし、「友・敵」を区別する原理は、文化を共有しているかどうかに基づいて定義される」と述べた。
ロシアには民族間の紛争などないし、かつてあったはずもない。ロシアはその本質からして、調和を生みだし他国に広める国であり、よって近隣諸国にロシア独自の平和をもたらすのは許されるべきことなのだ。
このユーラシア主義によれば、ウクライナ人とは、「カルパチア山脈からカムチャッカ半島までの」広大な土地に散らばるひとびとであり、よってロシア文明の一つの要素にしかすぎない。ウクライナ人が(タタール人、ユダヤ人、ベラルーシ人のように)もう一つのロシア人集団にほかならないとすれば、ウクライナの国家としての地位(ステートフッド)などどうでもよく、ロシアの指導者としてプーチンはウクライナのひとびとを代弁する権利を有することになる。だからこそ、プーチンはこう述べた。
「我々は何世紀にもわたりともに暮らしてきた。最も恐るべき戦争にともに勝利を収めた。そしてこれからもともに暮らしていく。我々を分断しようとする者に告げる言葉は一つしかないのだ――そんな日は決して来ない」
プーチンによれば、ヨーロッパとアメリカがウクライナを承認することで、ロシア文明に挑戦状を叩きつけたことになる。「ロシアは無垢なだけでなく寛容でもある」とプーチンは論じた。「ロシア文明を介してのみ、ウクライナ人は自分たちがほんとうは何者なのかを理解できる」のだから。
こうした世界観・歴史観からは、クリミアやウクライナ東部の占拠だけでなく、今回の全面侵攻も「無垢なロシア」を取り戻し、世界を救済し、神の完全性を復活させる壮大なプロジェクトの一部になる。そして今起きていることを見れば、スナイダーがこのすべてを予見していたことは間違いない。
だがここまで読めば、なぜ私がこの主張を受け入れるのを躊躇したのかわかってもらえるのではないだろうか。スナイダーが正しいとすれば、ロシアは巨大な「カルト国家」ということになってしまうのだ。
第2回 陰謀論とフェイクニュースにまみれた国
第3回 「プーチンの演出家」が書いた奇妙な小説を読んでみた
第4回 「共産主義の犯罪」をめぐる歴史戦の末路
第5回 ロシアはファシズムではなく「反リベラリズム」
第6回 30年前に予告されていた戦争
禁・無断転載