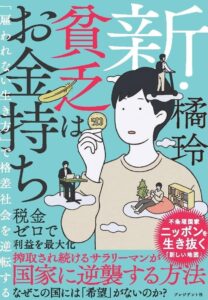明後日31日(月)発売の新刊『新・貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する』(プレジデント社)のまえがき「奇妙な世界を賢く歩くための地図」を出版社の許可を得て掲載します。すでに都内の大手書店などでは店頭に並んでいるようです(電子書籍も同日発売です)。
書店さんで見かけたらぜひ手に取ってみてください。
******************************************************************************************
本書は2009年6月に講談社から刊行され、11年3月に講談社+α文庫に収録された『貧乏はお金持ち 「雇われない生き方」で格差社会を逆転する』の内容を新しくしたものだ。幸いなことに親本は多くの読者を得ることができたが、それでも新版にしたのには理由がある。この16年のあいだに、話があべこべになってしまったのだ。
マイクロ法人は私の造語で、取締役一人か、役員が家族のみで構成される最小法人のことだ。自営業者が法人化すると、「個人」と「法人」のふたつの“人格”を持つことができる。
本書は「一人なのに二人」というこの不思議について書いているが、それを税・社会保険料コストの(合法的な)軽減に利用する場合、親本刊行当時の一般的なアドバイスは、「法人を赤字にして個人で納税する」だった。それがいまでは、「個人の所得を下げて法人で納税する」に180度変わってしまった。
その理由は本文で詳述するが、簡単にいうと次のようなことだ。
法人側の変化としては、「日本の法人税率は世界的に高い」という批判から、30%だった法人税率が2012年から18年にかけて段階的に23.2%まで引き下げられた。さらに、資本金1億円以下の法人は課税所得800万円以下の部分について22%の軽減税率が適用されていたが、世界金融危機を受けて2009年に18%に、次いで東日本大震災からの復興を名目に12年に特例として15%まで引き下げられた。また地方法人税も、(東京都の場合)本則は7%だが、課税所得800万円以下で5.3%、同400万円以下で3.5%に軽減されている。
その結果、親本では「マイクロ法人の(国税と地方税を合わせた)実効税率は30%」としていたのが、現在の実効税率は最低で18.5%まで下がっている。
それに対して個人所得税は、課税所得に対して5%から最高45%の累進課税で、住民税(東京都)の所得割は定率の10%だから、実効税率は15%から最高55%だ。そうなると、ほとんどの場合、個人よりも法人で納税したほうが有利になるだろう。これが「あべこべ」になった第一の理由だ。
*
もうひとつは個人の側の変化で、じつは親本では法人の役員が国民年金と国民健康保険に加入することを前提にしていた。当時も法律上は、役員1人の法人でも社会保険に加入しなければならなかったが、これはあくまでも建て前で、どちらも公的社会保険制度なのだから、家族経営の零細法人は国民年金/国民健康保険と社会保険のどちらか有利なほうを選べばいいというのが実態だった。
人類史上未曾有の超高齢化によって日本の財政は逼迫しており、社会保険料の負担は大幅に上がっている。本書の親本が刊行された2009年当時、厚生年金の保険料率は15.704%だったが、それが現在(2025年)は18.3%になっている。同じく中小企業が加入する協会けんぽの保険料率は、40歳以上が支払う介護保険料込みで(自治体の平均で)9.39%から11.6%に上がった(同時に、保険料を支払う収入の上限も引き上げられ、高所得の会社員の負担が重くなっている)。
これをわかりやすくいうと、年収600万円のサラリーマン/サラリーウーマンの場合、2009年には(ボーナスをならして)月額50万円の給与に対して約6万3000円の社会保険料が天引きされていたが、それが現在は約7万5000円に増えている。この16年間で、毎月の手取りが1万2000円(年額14万4000円)も減ってしまったのだ。
あなたが給与明細を見て、「会社はベースアップしたというけれど、手取りは逆に減っているじゃないか」と疑問に思ったら、その理由は増税ではなく、社会保険料の負担増だ(会社が支払う社会保険料も同じだけ上がっているので、会社はその分、人件費を抑制しようとするだろう)。
消費税を上げようとすると国会で紛糾必至で、政権がいくつもつぶれるが、社会保険料率の引き上げは厚生労働省の一存でできるので、この「ステルス増税」が常態化している。その結果、日本の社会保障制度の歪みはますます大きくなっている。
*
会社員が加入する社会保険と、自営業者が加入する国民年金/国民健康保険ではどちらが得なのか。厚生年金の保険料が収入に応じて決まるのに対して、国民年金の保険料は定額(2025年時点で月額1万6980円)なので、この比較は簡単だ。
年収600万円の会社員の厚生年金保険料は、自己負担のみで年額約55万円(会社負担分を含めると約110万円)だが、国民年金なら年収にかかわらず年額20万円強だ。掛け金が少ないと将来の年金は減るが、厚生年金保険料との差額の35万円をNISA(ニーサ)で非課税で運用したほうが老後資金はずっと大きくなるだろう。
ここまではシンプルだが、話がややこしくなるのは、国民健康保険の保険料が、社会保険の会社負担分と自己負担分の合計に見合うように引き上げられてきたことだ。その結果、会社員が自己負担する健康保険料が年額30万円だとすると、生活水準が同じ自営業者は年額60万円の保険料を支払わなくてはならない。そのうえ社会保険では扶養家族の健康保険は無料だが、国民健康保険は本人分のみなので、配偶者・子ども・親など扶養家族がいれば、その分の保険料を別で納めなくてはならない。│自営業者から「国民健康保険の保険料負担が重すぎる」という不満の声が上がるのはこれが理由だ。
これはたしかに理不尽だが、一人二役のマイクロ法人では、自己負担だけでなく会社負担の保険料も支払わなくてはならないから、扶養家族の人数にもよるが、「国民年金は厚生年金より有利で、国民健康保険の負担額は(労使合計では)社会保険と同じ」になる。さらに、かつては国民健康保険料の上限は60万円程度で、いったん上限に達すればそれ以上保険料は増えないから、個人の所得を大きくして法人を赤字にすることが「王道」とされていたのだ。
ところがその後、厚生労働省はできるだけ多くの労働者を社会保険に加入させるという方針を徹底するようになり、年金事務所は従業員10人以上の法人を重点調査すると同時に、マイクロ法人にも社会保険の加入義務があることを通知しはじめた。それに加えて国民健康保険の保険料の上限が109万円(介護分を含む)に引き上げられ、その一方で法人税の税率が引き下げられたことで、「個人の所得を小さくして社会保険に加入し、法人で納税する」というまったく逆のやり方のほうがコスパ(費用対効果)がよくなったのだ(それに法律も遵守できる)。
社会保険料は収入(標準報酬月額)によって決まり、会社負担分と自己負担分を合わせて収入のおよそ30パーセントだ。社会保険料(労使合計)は役員報酬600万円で180万円だが、報酬が300万円なら90万円と半額になる(最低額は年収75万6000円未満にしたときの年額約27万4000円)。──役員報酬を下げれば社会保険料は安くなるが、(扶養家族の保険を含む)健康保険のメリットは変わらない。
このようにして、親本のアドバイスは16年で「あべこべ」になってしまった。私はずっとこのことを気にしていたが、親本の編集を担当してくれた村上誠さんがプレジデント社に移籍し、声をかけてくださったことで、PART4「磯野家の節税──マイクロ法人と税金」の部分を全面的に書き換えて新版にすることにした。
ただし、「法人とはなにか?」という話や税・社会保障の仕組み、超低利融資が可能になる理由など、それ以外の部分はできるだけ親本の記述を活かすことにした。このような文章はいまの自分には書けないということもあるし、日本社会の制度の歪みがほとんど変わっていないということでもある(数字は適宜、最新のものに置き換えた)。
また親本では、コラムとして会社の設立方法、法人税の申告、公的融資制度の利用方法などを具体的に記述したが、制度の細則は頻繁に変更されるし、いまではネット上に懇切丁寧な解説がたくさんあるので、すべて削ることにした(そのかわり、「副業で節税できるか?」と「補助金を受け取る」のコラムを加えた)。
2024年の衆議院議員選挙をきっかけに、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」が注目されることになった。だがほとんどのひとは、それがなんなのかうまく理解できないだろう。それほど日本の税・社会保障制度は複雑怪奇なのだ。
本書を、そんな奇妙な世界を賢く歩くための地図として使ってもらえればうれしい。
2025年2月 橘玲