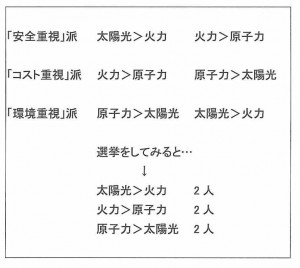新刊『大震災の後で人生について語るということ』から、「はじめに」の文書を転載します。
* * * * * * * *
歴史には、ある一瞬で世界の風景を変えてしまうような出来事があります。それはたとえば、フランス革命でバスティーユ牢獄を襲った暴徒たちであり、イギリスの植民地政策に抗議してボストン湾に捨てられた紅茶箱であり、第一次世界大戦の引金を引いたサラエボでの一発の銃弾のことです。現代史に目を移せば、ベルリンの壁崩壊や9.11同時多発テロで世界の姿は大きく変わりました。そしておそらく、3.11の東日本大震災とそれにつづく福島第一原子力発電所事故で、日本の社会は引き返すことのできない橋を渡ることになるでしょう。これから私たち日本人は、否応なくポスト3.11の世界を生きることになるのです。
もちろんある歴史上のある出来事によって、昨日と今日がまったくちがう世界になるわけではありません。
冷戦が終焉してソヴィエト連邦が解体したのち、イスラム圏に民族主義や原理主義が台頭しつつあることは繰り返し報じられていました。アフガニスタンで大量の麻薬が製造されていることも、石油をめぐって国家や民族集団の利害が対立していることも、イスラム原理主義のグループがアメリカをはじめとする西欧社会をテロの標的にしていることも広く知られていました。しかし、それらはジグソーパズルのばらばらのピースにしかすぎず、9.11がすべてのピースを組み合わせ、世界の風景を一変させるまで、私たちはひとつひとつの事件が密接につながり合い重なり合っている姿を見ることはできなかったのです。
この本は、私たちの世界を変えた「2つの災害」について書かれています。ひとつはもちろん東日本大震災と原発事故、もうひとつはいまから14年前に日本を襲い、累計で10万人を超える死者を出した「見えない大災害」です。
この「見えない大災害」によって戦後は終わり、日本は新しい社会へと移行しはじめました。しかしほとんどのひとはこのことに気づかず、3.11によってはじめて、私たちはこれまで目をそむけていた人生の経済的なリスクに正面から向き合わざるを得なくなったのです。
*
ところで、リスクとはいったいなんでしょう。さまざまな定義があるでしょうが、この本では、「欲望と同様に、それによってひとびとの行動を規定するもの」と考えます。危険に遭遇すると、生き物は反射的に身を守ろうとします。同様に私たちは、無意識のうちに危険を回避する選択をしており、リスクに対する耐性(許容度)はひとによって大きく異なります。
震災翌日の3月12日に、福島第1原発1号機で水素爆発があり、原子炉建屋が大きく損傷しました。週明けからの計画停電が発表されたこともあり、電器店では乾電池や懐中電灯が売り切れ、パンやカップ麺などの保存食品がスーパーからまたたくまに消えました。
その後も時を追うごとに原発事故の深刻さは増し、14日に3号機の建屋が水素爆発で吹き飛び、翌15日には安全なはずの4号機で過熱した使用済み核燃料プールから火の手があがりました。この頃には、首都圏でもガソリンスタンドに給油を求める長い車の列ができていました。さらに23日、東京・葛飾区の金町浄水場で基準値を超えるヨウ素が検出され、乳児への摂取制限が発表されると、ひとびとはペットボトルの水を求めてスーパーやコンビニに殺到しました。
このパニック的な購買行動が問題視されたのは、被災地でも物資やガソリンが大幅に不足していたからです。「首都圏で買い占めが起こると、それだけ被災地に送る物資が減ってしまう。どちらの緊急性が高いかは明らかなのだから、首都圏の消費者は不要不急の買い占めをいますぐ止めるべきだ」――たしかに正論ですが、問題はそれほど単純ではありません。
ひとはだれでも、危機に際して最悪の事態を想定し、そのなかで最善の選択肢を探そうとします。
スーパーのレジに並んでいた足の悪い高齢者は、原子炉が爆発し、高濃度の放射性物質が首都圏を覆い、退避命令が出されたとき、自分だけが見捨てられるのではないかと怯えていました。ガソリンスタンドで何時間も給油を待つレジャービークルの若い男性は、生まれたばかりの子どもを抱えていて、車がなければ家族を守ることができないと考えています。不確実な状況ではこれはきわめて合理的な行動ですから、電車でも自転車でも徒歩でも移動できる(私のような)人間が買い占めを批判することはできません。一見、利己的に見えたとしても、リスク耐性の低いひとたちにはやむにやまれぬ事情があるのです。
このことからわかるように、不安が生じるのは、自分が抱えているリスクが管理できる範囲を超えていると感じるからです。買い占めを倫理的に批判することに意味はなく、この問題を解決するには一人ひとりのリスク耐性を上げるか、リスクに強い社会を築き上げていくほかはありません。
しかしこれから本書で述べるように、私の危惧は、日本人も日本社会もますますリスクに対して脆弱になっているのではないか、ということにあります。日本社会をいま大きな不安が覆っているとすれば、そのひとつの(そしておそらくはもっとも大きな)理由は、日本人の人生設計のリスクが管理不能になってきたからです。
これから、戦後の日本人の人生設計を支配してきた4つの神話が崩壊してきた様を順に述べていきます。それは「不動産神話」「会社神話」「円神話」「国家神話」で、人生の経済的な側面からいえば、ポスト3.11とは「神話」を奪われた世界を生きることです。
しかし私たちは、いまだに“神話なき時代”の人生設計を見つけることができず、朽ちかけて染みだらけの設計図にしがみついています。そしてこの役に立たない設計図から生じるリスクが、日本人の行動を規定しています。皮肉なことに、私たちはリスクを避けようとして、そのことで逆にリスクを極大化させ、それが不安の源泉になっているのです。
3.11は、これまで大切にしてきたものが暴力的に奪われ、破壊される光景を私たちに見せつけました。
未来は不確実で、世界はかぎりなく残酷です。明日は今日の延長ではなく、終わりなくつづくはずの日常はふいに失われてしまいます。
しかしそれでも私たちは、そこになんらかの希望を見つけて生きていかなければならないのです。
『大震災の後で人生について語るということ』P1~5