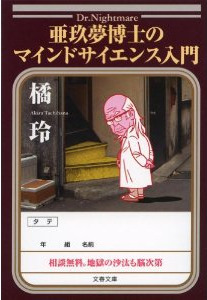石原東京都知事が尖閣諸島購入の意向を明らかにしたことで、日中間の緊張が増しています。このやっかいな問題について目新しい提案ができるわけではありませんが、ここではなぜ領土問題の解決が困難なのかを考えてみましょう。
国家のもっとも重要な役割は、国民のために「国益」を守ることだとされています。当然だと思うでしょうが、「国益とはいったいなにか」を問われるとこたえに窮してしまいます。
TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)問題では、参加を阻止することが日本の国益だと主張するひとたちがたくさんいます。彼らの主張では、TPPはアメリカの陰謀で、日本が加盟すれば農業は壊滅し、医療保険は崩壊し、金融市場は外資に乗っ取られてしまうのです。
それに対して、TPPに参加することが日本の国益だというひとたちもいます。彼らは、市場がますますグローバル化するなかで日本だけが貿易自由化に反対していては、いずれ世界の孤児になってしまうと警告します。
原発問題でも、「国益」をめぐって議論は激しく対立しています。
原発反対派のひとたちは、原発の再稼動をひとつでも認めれば国民の生命が危険にさらされると危機感を募らせます。その一方で、電気料金の大幅値上げによって国内の製造業が壊滅し、空洞化で雇用が海外に流出してしまうと考えるひともいます。
消費税問題はどうでしょう。
増税に反対するひとたちは、日銀が国債を引き受けて市場に大量のマネーを供給すれば日本経済はデフレの病を克服し、ふたたび経済成長できると主張します。消費税引き上げを支持するひとは、そんなことをすれば国家財政が破綻して、日本はギリシアのように極東の貧しい国に落ちぶれてしまうといいます。
このように、あるひとにとっての国益は、別のひとにとっては亡国の道です。両者は激しく憎み合っていて、妥協はもちろん話し合うことすらありません。
現代の政治学では、「国益」というのは国家の名を借りた「私益」のことだとされています。
TPPで安い外国産農産物が流入する農家にとっては参加阻止が国益で、外国企業と同じ条件で競争したい製造業にとっては早期の参加が国益です。増税で年金や医療などの社会保障を維持することが国益だと考えるひともいれば、徹底した歳出削減によって税金を引き下げることが国益のひともいるでしょう。
しかし国益のなかに、ただひとつだけ国民の全員が同意するものがあります。それが領土です。
「北方領土は返ってこなくていい」とか、「日中友好のために尖閣諸島は中国に割譲しろ」と主張する日本人はいません。国民の利害が多様化し、政治的な対立が先鋭化するなかで、領土こそが国家をひとつにまとめるかすがいになるのです。
しかしこのことは、領土問題が原理的に解決不可能なことを教えてもくれます。ロシアや中国の国内でも私益が激しく対立して、権力の基盤を揺るがしています。だからこそ、“唯一絶対”の国益である領土問題ではわずかたりとも譲歩できないのです。
東京都が購入しようが、日本政府が国有化しようが、尖閣問題が解決することはありません。国家が存在するかぎり、領土をめぐる対立は未来永劫つづいていくのです。
『週刊プレイボーイ』2012年8月6日発売号
禁・無断転載