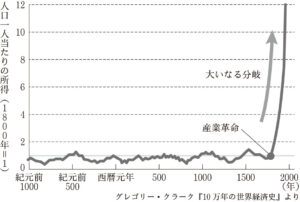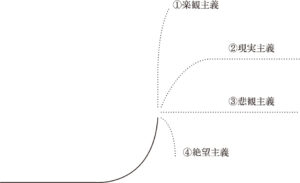18日発売の新刊『新・臆病者のための株入門』(文春新書)の「新版・あとがき」を出版社の許可を得て掲載します。書店の店頭で見かけたら手に取ってみてください(電子書籍も発売中です)。
 ******************************************************************************************
******************************************************************************************
親本のあとがきに「ひとには、正しくないことをする自由もあるからだ」と書いたが、2006年当時の私は、新興国の銀行・証券会社に口座を開設し、現地通貨で預金したり、株式を購入することにはまっていた。東アジアと東南アジアが中心で、モンゴルとミャンマーを除けば、ほぼすべての国に口座をつくった。インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシアなど、どこも思い出があるが、珍しいのはカンボジアとラオスの銀行・証券口座だろう。
この本を書いている頃は、イラクに行って銀行口座を開くことを考えていた。アメリカ軍によって2003年にフセイン政権が崩壊したのち、イラクは内戦状態に陥るが、北部のクルド人地区は自治領のようになっていて治安もよく、銀行から招待状を出してもらえば現地に行って口座開設することが可能だったのだ。
イラクの通貨ディナールはフセイン政権末期に暴落したが、アメリカの占領で治安が回復すれば、石油収入によってディナールは上昇し、大きな利益が期待できるといわれていた。
私はこの話を信じていたわけではないが(案の定、その後はディナール詐欺の温床になった)、イラクに行ってみるのは面白そうだと思っていたのだ。だがぐずぐずしているうちにイラク北部でも民族紛争が始まり、アラブの春以降はイスラーム原理主義の武装組織のテロ活動が激しくなって、やがて「イスラム国」の樹立が宣言されることになる。
すくなくとも当分のあいだ、イラクを旅できるようにはなりそうもないので、やはりあのときに行っておけばよかったと残念に思う。
これも親本のあとがきに書いたが、人的資本を執筆活動に集中させることにしてから、海外の株式はほとんど売却して外貨にしてしまった。その時期が2008年の世界金融危機の前だったのは、慧眼ではなく、たまたま運がよかっただけだ。
こうして振り返ると、1990年代末から2000年代はじめの10年にも満たない間に、インターネットバブルと新興国バブルという大きな2つのバブルに遭遇することができたのは、ほんとうに幸運だったと思う。
私の場合、「正しくない投資」によっていろんな体験ができた(あちこちの国に知り合いもつくれた)が、誰にでも勧めようとは思わない。限られた時間のやりくりに四苦八苦しているひとにとっては、コスパだけでなくタイパも優れた「経済学的に正しい投資法」がやはり最強だろう。
これは私が書いたもののなかでも長く読まれる本になったが、この新版で新たな読者に手に取ってもらえるとうれしい。
2024年10月 橘 玲