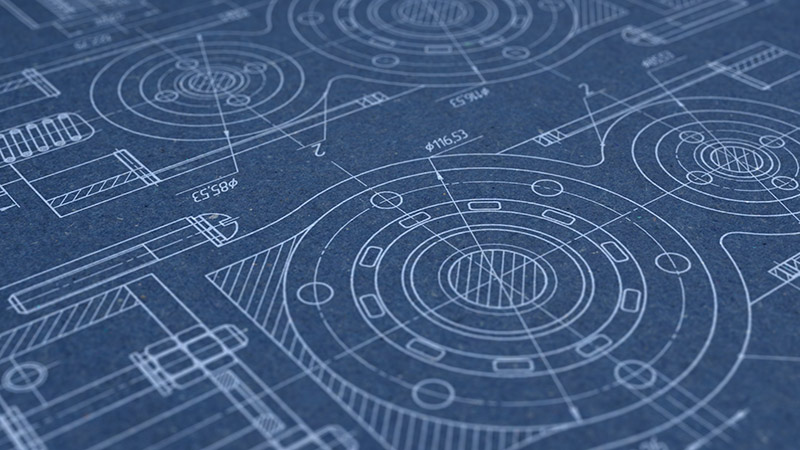2024年は「選挙の年」として記憶されることになるかもしれません。
10月に行なわれた衆院選で自民・公明の連立政権が少数与党に転落し、「政治とカネ」問題に注目が集まりましたが、世界の大きな流れのなかに置くとまた別の景色が見えてきます。
4月の韓国総選挙では与党「国民の力」が大敗し、議席数は野党勢力の半分になってしまいました。国会運営に行き詰まった尹錫悦大統領は「非常戒厳」を宣布する大博打を打ったものの、野党の抵抗で24時間もたたないうちに撤回を余儀なくされる予想外の展開になりました。
これほど極端でなくても、それ以外の重要な選挙でも政権党は敗北するか、苦戦しています。
接戦が伝えられていた11月の米大統領選では、ドナルド・トランプが激戦州をすべて制しただけでなく、上院・下院で共和党が過半数を占める「トリプルレッド」となり、バイデン=ハリスの民主党は大きな打撃を受けました。
14年ちかく保守党政権が続いてきたイギリスでは、7月の総選挙で野党・労働党が単独過半数を獲得して政権交代を実現しました。
フランスでは欧州議会選挙での敗北を受けて、マクロン大統領が国民議会を解散し、オリンピック前に総選挙を行なう賭けに出ましたが、「不服従のフランス」などの左派政党と、右派政党の「国民連合」が票を伸ばし、マクロン大統領率いる中道連合の議席は改選前の3分の2まで減りました。その結果、バルニエ首相の少数内閣は予算案で行き詰まり、不信任決議で首相の交代を余儀なくされました。
さらにドイツでは、11月にシュルツ首相が財務省を解任したことで連立の枠組みが崩れ、少数与党のまま政権を維持することは難しく、来年3月の総選挙が予定されています。
6月に行なわれたインドの総選挙でも、圧勝が予想されていたナレンドラ・モディ首相のインド人民党(BJP)が大きく議席を減らし、かろうじて与党連立で過半数を維持しました。
それぞれ事情の異なる国で同じようなことが起きているのは、たんなる偶然ではなく、そこには共通する要因があります。
新型コロナ感染症のパンデミックとロシアのウクライナ侵攻を受けて各国で物価が上昇しましたが、賃金の上昇がそれに追いつかず、ひとびとの生活は苦しくなっています。ヨーロッパではこれに移民政策への不満が結びついて、“極右”政党への支持が広まりました。米大統領選でトランプ陣営が移民問題で過激な主張を繰り返したのは、欧州の政局から、それが票につながることを知っていたからでしょう。
シリアのアサド政権が崩壊するなど、世界ではいまも多くの重大事件が起きていますが、国民にとって重要なのは、自分の生活がゆたかになるかどうかなのです。
1992年の米大統領選では、冷戦の終結や湾岸戦争の勝利という歴史的な“偉業”を成し遂げたブッシュ(父)大統領に挑んだクリントン陣営は、“It’s the economy, stupid.(けっきょくは経済なんだよ、愚か者)”を掲げて大番狂わせを起こしました。そう考えれば、いま起きているのは「民主主義の危機」ではなく、その頃から民主政(デモクラシー)の本質はなにも変わっていないのでしょう。
『週刊プレイボーイ』2024年12月23日発売号 禁・無断転載