ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。
今回は2016年3月31日公開の「最後発の日本と違い、大航海時代から始まった植民地支配をいまさら「反省・謝罪」をしない欧州・フランスの事情」です(一部改変)。
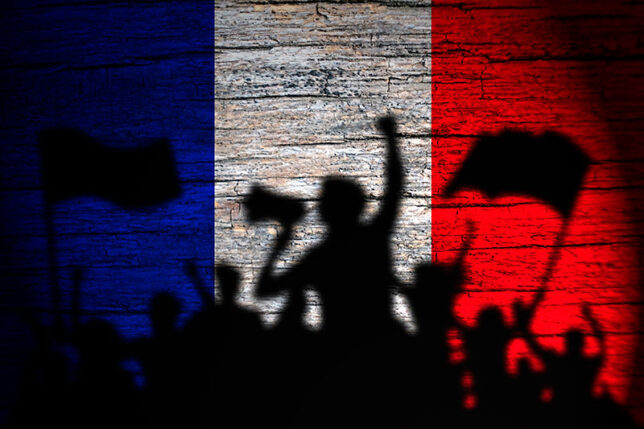
******************************************************************************************
2016年3月22日、ベルギーでIS(イスラム国)による同時テロが発生し、空港と地下鉄で30人以上が死亡する惨事となった。世界でもっとも安全なはずのヨーロッパでテロが頻発するようになった理由はさまざまだろうが、私の理解では、その深淵には長い植民地支配の歴史がある。
近現代史をみれば明らかなように、日本は最後発の「帝国」で、最初の帝国主義戦争は1894年の日清戦争、朝鮮半島を植民地化したのは1910年だ。それに対してヨーロッパ列強がアフリカ、南北アメリカ大陸を侵略し、奴隷制で栄えたのは15世紀半ばの大航海時代からで、イギリスが東インド会社を設立してインドなどを次々と植民地化したのは1600年代だ。フランスのアルジェリア支配も1830年から1962年まで130年に及ぶ。日本とはその規模も影響力も桁ちがいだ。
私見によれば、これが日本が中国・韓国などから過去の歴史の反省と謝罪を求められる一方で、欧米諸国が植民地時代の歴史を無視する理由になっている。日本の場合は謝罪や賠償が可能だが、ヨーロッパの植民地支配は現代世界の根幹に組み入れられており、いまさらどうしようもないのだ――イスラエルとパレスチナの対立はヨーロッパのユダヤ人差別と第二次大戦中の場当たり的なイギリスの外交政策が引き起こしたが、だからといって過去を「反省・謝罪」したところでまったく解決できないだろう。
そのためヨーロッパでは、「植民地時代の過去」は日本とはまったく異なるかたちで現われる。
前回は、2005年にフランス国民議会で与野党の圧倒的多数で可決された「(アルジェリアからの)引き揚げ者への国民の感謝と国民的支援に関する法(以下、引揚者法)」を紹介した。私たち日本人が驚愕するのは、この法律の第4条1項で、「大学などの研究において、とりわけ北アフリカにフランスが存在したことについてしかるべき位置を与える」と定め、さらに第2項で、(高校以下の)学校教育において「海外領土、なかでも北アフリカにフランスが存在したことの肯定的な役割」を認める、と明記したことだ。
この第4条2項はその後、紆余曲折を経て廃止されることになるのだが、今回は平野千果子氏の『フランス植民地主義と歴史認識』(岩波書店)と、高山直也氏(国立国会図書館海外立法情報室)のレポート「フランスの植民地支配を肯定する法律とその第4条第2項の廃止について」に拠りながらその経緯を見てみたい。
2000年のアルジェリア大統領の訪仏で起きた「歴史問題」
フランスとアルジェリアの1世紀におよぶ支配と抵抗の複雑な歴史については前回述べたが、2005年引揚者法が制定される直接のきっかけになったのは2000年6月のブーテフリカ・アルジェリア大統領の訪仏だった。
フランス国民議会での演説でブーテフリカ大統領は、フランスが植民地時代に行なってきたことに対する「悔悛」を求めた。またテレビ出演した際に、アルキ(アルジェリア戦争をフランス側で戦ったアルジェリア人。戦後、約5万人がフランスに逃れたとされる)をヴィシー政権時代のナチ協力者と同じ「対敵協力者(コラボ)」と断じ、彼らの里帰りを拒否した。
アルジェリア大統領の訪仏に合わせるように、高級紙『ル・モンド』(2000年6月20日)の一面に、アルジェリア戦争中にフランス軍に逮捕・拷問されたというFLN(アルジェリア民族解放戦線)闘士の女性の証言が掲載された。その2日後、こんどは拷問を指揮したと名指しされた将軍が事実を認めるとともに、遺憾の意を表明する記事が掲載されるのだが、同日の別の紙面では、同じく名指しされたもう一人の将軍が告発の内容を全面的に否定し、「彼女には会ったこともないしこれは詐術にすぎない」と反論した。
さらに翌日の紙面で、ポール・オサレスという別の将軍が、拷問に自ら手を下したことを認めたうえで、それを正当化した。オサレスは翌年、アルジェリア戦争を回顧した『特別任務』を刊行するのだが、「拷問でアルジェリア人から情報を得てテロを未然に阻止し、無実の人たちを救ったのであり、拷問は効率的で正当であった」と述べたのだ。この著作刊行後、オサレスは人権団体から「人道に対する罪」で提訴されている(オサレスはさらに、アルジェリア側についたフランス人の共産党活動家の拷問死に関与したとして訴えられた)。
アルジェリア戦争を「汚い戦争」として見直すこうした動きに対し、ピエ・ノワール(黒い靴)と呼ばれるアルジェリアからの引揚者やアルキたちが反発し、それに右派・保守派の議員たちが呼応して、彼らの名誉を守るための法律制定が模索されるようになる。
「植民地国の和解や協力のためには「感謝」が先行すべきだ」
その最初の試みが、2003年に100人以上の保守派(UMP国民運動連合)議員によって国民議会に提出された「フランスが存在した期間、アルジェリアで生活していたわが同胞のすべての肯定的業績を認めることを目的とする法案」で、この法案は次の単一条文からなっていた。
第1条 フランスが存在した期間アルジェリアで生活したすべてのわが同胞の肯定的業績は公に認められる。
この法案は、その趣旨説明で以下のように述べている(高山氏前掲論文)。少し長いが、フランスの「植民地意識」がよく現われているので全文を引用しよう。
フランスは1830年から1847年にアルジェリアを征服して植民地としてから1962年にアルジェリアが独立するまで、科学・技術や行政についてのノウハウや文化、言語をこの地にもたらした。
アルジェリアが発展したのは大部分は入植者たちの勇気と進取の精神のおかげであり、フランスとアルジェリアの両国が苦しみと誤解、惨劇、身内同士の殺し合いにもかかわらず、文化的に、また深く結ばれているのは、大部分は彼らのおかげである。
シラク、ブーテフリカ両大統領によって2003年が「フランスのアルジェリア年」とされたこのような機会に「アルジェリアにおけるわが同胞の肯定的業績」を思い起こさないとすれば、それはアルジェリア戦争で大きな犠牲を払った兵士やアルキを讃え、感謝を表明しないことが過失となるのと同じように、歴史的誤りとなるであろう。
「記憶と感謝の時が和解と尊敬と協力の時に先行する」。
だからこそ、フランスとアルジェリアが両国を深く結びつける絆を強化し、深めることができるためには、国民の代表である国民議員がこれら多くの男女の業績を認めることが望ましいし、また正当でもあるように思われる。
前回、フランスの歴史家ジャック・マルセイユが「旧宗主国はおしなべて植民地から感謝されるべきであり、日本も韓国から感謝してもらってはどうか」と日本での講演で述べたことを紹介したが、これを読むとマルセイユの主張がフランスでは奇異なものでないことがよくわかる。ここでは、旧宗主国と植民地国の和解や協力のためには「(被植民地の)感謝」が先行すべきだとはっきり述べられているのだから。
2003年提出の法案はけっきょく成立しなかったが、それを受けてUMPのラファラン首相はミシェル・ディーフェンバッハ国民議会議員に、引揚者関係法の分析と今後の対応についてまとめるよう要請した。2005年引揚者法は、このディーフェンバッハ報告に基づいている。
この報告書は、「学校教育」の項で次のように述べている(高山氏前掲論文)。
アルジェリア戦争のように最近の、感情がからむ事件の記述に非の打ち所のない客観性を求めることはむつかしいとしても、「引揚者高等評議会」が数種の学校教科書から抜粋した記述を読むと、暴力を振るったのはフランス側だけのような書き方がしてある。その一方でアルジェリアが(アルジェリア戦争の終戦を定めた)エビアン協定を守らなかったことやこの休戦協定に続いておこったアルジェリアにおける虐殺や行方不明についてこれらの教科書が黙っていることは疑問を呼んでいる。
さらにディーフェンバッハ報告は、「奴隷売買及び奴隷制が人道に対する罪であることを認めることを目的とする2001年5月21日の法律」の第2条が「学校の教科及び歴史若しくは人文科学の研究科目は、奴隷売買及び奴隷制に対してそれにふさわしい重要な位置づけを与えなければならない」としていることを根拠に、出版社の自由や学問の世界の独立は絶対の基準ではないと主張してもいる。歴史教科書への介入は、この時点ですでに予定されていたのだ。
「アルジェリア系の若者たちを社会に統合するためには、植民地化の肯定的な側面を学校教育で教えるべきだ」
2005年引揚者法は与野党の圧倒的多数で国民議会で可決されたが、その直後から、(歴史教育を定めた)第4条2項に対して歴史学者などから強硬な反対が起こる。彼らは『ル・モンド』紙に「植民地化――公的な歴史にノン」と題する声明文を寄せ、この法律が学校教育の中立性および思想の自由に反して公式の歴史を強制し、植民地化の否定的な側面(虐殺、奴隷制、人種差別など)を隠蔽し、過激なナショナリズムの分離主義を引き起こすと批判した。
こうした批判に対し、アムラウイ・メカシェラ退役軍人担当相は次のように反論した(高山氏前掲論文)。
もしわれわれが引揚者やアルキの苦しみを和らげようと思うならば、われわれはまず彼らがしてきたことや耐え忍んだことの現実を認めるべきである。植民地化の肯定的な面を認めることは、それがもっていたかもしれない暗い面を否定することではない。
またアルジェリア出身の若者たちを統合しようと思うなら、20世紀の戦争において彼らの先輩たちが重要な役割を果たしたことを教えなければならない。アルジェリアとの関係についても、もしわれわれがわれわれのパートナーであり友人となった国々と強力で持続的な新たな関係を築こうと思うならば、歴史を直視しながら、アルジェリア出身の若者たちにそのことを教えなければならない。
2003年提出の法案は、「旧宗主国と植民地国の和解や協力のためには「(被植民地の)感謝」が先行すべきだ」との論理に基づいていた。2005年の引揚者法ではそれに加えて、「フランス国内に暮らすアルジェリア系の若者たちを社会に統合するためには、植民地化の肯定的な側面を学校教育で教えるべきだ」との論理が登場したのだ。
2005年引揚者法の4条2項はけっきょく削除されることになるのだが、それは歴史学者たちの批判が世論の支持を集めたというよりも、同年11月に勃発した大規模な暴動と、その余波の影響が大きい。暴動のきっかけは警官に追われた移民の若者2人が変電所の電線に触れて感電死したことで、サルコジ内相が郊外の若者たちを「ラカイユ(社会のくず)」と呼んだことが火に油を注いだ。
暴動を沈静化させるために政府は第4条を削除する法案を提出するが、与党議員らによって否決されてしまう。するとそれに反発してカリブ海のフランス海外県マルティニークで抗議デモが広がり、サルコジの訪問が拒否される事態にいたった。こうした混乱でシラク大統領は第4条2項の廃止を決めるが、ふたたび国民議会で否決されるのを避けるために法案を憲法評議会に付託し、条文が憲法に反するという判断を得て削除されることになったのだ。
フランスでは左派も植民地主義に肯定的
ここまで平野千果子氏と高山直也氏の著作に基づいてフランスの2005年引揚者法が引き起こした騒動を紹介してきたが、なぜこのような、われわれ日本人の「常識」からはとうてい考えられないことが起きたのだろうか。
ひとつは、ピエ・ノワールやアルキといった“故郷を追われた”ひとたちがフランス現代史の暗部であり、国家と歴史の被害者であるという認識が広がってきたことだろう。とりわけアルキは軍の施設などに隔離され、フランス国内ですらその存在はほとんど知られていなかった。“国家の恥部”として隠蔽され、差別に苦しんできた彼らの名誉を回復し、補償すべきだという主張は、保守派だけでなくリベラルのひとたちにもじゅうぶんな説得力を持つものだった。
アルキが在日韓国朝鮮人と異なるのは、“アルジェリア人”のアイデンティティを喪失した彼らが完全な“フランス人”になることを望んでいることだろう。フランスの同化主義からすれば、兵士として国家に貢献し、完璧なフランス語を話し、フランス革命の普遍的な価値を認めるひとびとを拒む理由はない。そのうえ彼らは「フランスのアルジェリア支配はよい時代だった」と、フランス人の耳の心地いい“歴史観”を語ってくれるのだ。
だがそれ以上に興味深いのは、フランスの露骨な(と日本人からは思える)植民地肯定論に、かつての植民地から表立った批判が聞こえてこないことだ。これが日本と中国・韓国との関係の際立ったちがいで、「日本の植民地支配は野蛮で残酷だが、欧米の植民地政策は文化をもたらした」とのステレオタイプが生まれる理由となっている。
これについて平野千果子氏は、それぞれの旧植民地ごとに異なる事情を説明している。
もっとも古いカリブ海の植民地では、ハイチは1804年にフランスから独立したが、マルティニークやグアドループ、フランス領ギアナはいまもフランスの海外県のままだ。インド洋のレユニオンや海外準県であるフランス領ポリネシアもそうだが、これらはそもそも国家として独立するには小さすぎる島や地域で、フランスに属して財政的な援助を受ける以外に生きていく方途がない。
そのため彼らの要求は、「フランスの一部」として、フランス人と平等な権利を獲得することになる。もちろん彼らのなかにも、有色人種であることで差別されているという不満はあるだろうが、それが「植民地支配」への批判につながることはない(カリブ地域では、ドゴールは奴隷を解放した共和主義の正統な後継者として神格化されている)。
フランスは東南アジアにも植民地を持っていた。「インドシナ」と呼ばれるベトナム、カンボジア、ラオスで、ハノイやホーチミン、プノンペン、ビエンチャンなどの都市は植民地時代のフランス風の街並みがいまも残されている。
だがこれらの地域にはベトナム戦争やポルポトの独裁のような、フランスとの独立戦争よりはるかに大きな影響を与えた現代史の出来事がある。さらにベトナムの場合、喫緊の課題はアメリカとの“戦争の記憶”ではなく、強国化する中国との安全保障上の対立だ。
「敵の敵は味方」の論理によってベトナム国民の対米感情はすっかり好転し、フランス植民地時代にいたっては「古きよき日々」になった(同様に第二次世界大戦中の日本の支配もまったく問題にされず、対日感情はきわめていい)。これではフランス側に、インドシナでの植民地支配を「反省」する理由があるはずはない。
それでは、フランスがもっとも広大な領土を支配したアフリカの国々はどうなのだろうか。これについては話が長くなるので、次回、紹介することにしたいが、その前にフランスのひとびとが植民地時代をどう考えているのか見ておきたい。
2005年12月に行なわれた世論調査では、フランス国民の64%が2005年引揚者法の(アルジェリア植民地時代の肯定的な役割を中学・高校の歴史で教えるという)第4条に賛成している。支持者別の内訳は、右派である国民運動連合(UMP)79%、フランス民主同盟55%のほか、左派の社会党55%、緑の党59%、共産党68%となっている。フランスでは「リベラル」もまた、植民地主義の肯定的な評価を法制化すべきだと考えていたのだ。
禁・無断転載
