日本的雇用慣行がなかなか変わらないのは、それが均衡解として安定しているからだ。でもナッシュ均衡は、いったん成立すると未来永劫変わらないというわけではない。
左側通行と右側通行を変えるのはものすごく大変だ。でも沖縄では、敗戦による占領で交通ルールがアメリカと同じ右側通行になり、本土復帰6年めの1978年7月30日に左側通行に戻された。このときは、わずか8時間ですべての道路標識・標示が変更されたという。
ここに、ナッシュ均衡のもうひとつの特徴がある。それはきわめて頑健だけれど、いったん状況が変わると一瞬のうちにもうひとつの均衡解に移ってしまうのだ(右側通行と左側通行が混在することはない)。
雇用慣行がナッシュ均衡だとすれば、日本的雇用がアメリカ型になったり、アメリカ的雇用が日本型になったりすることも考えられる。どのような条件で、このような変化が起きるのだろう。
面倒な説明は省略するけれど、青木昌彦によれば、雇用慣行がどちらの解に至るかは、期待賃金(労働供給関数)と実質賃金(限界生産性曲線)の関係で決まる。サラリーマンの実質賃金が期待賃金より大きければ、すべての労働者が正社員を目指し日本的雇用に至る。逆に実質賃金が期待賃金よりも低くなれば、サラリーマンはいなくなってアメリカ的雇用という均衡解に達する。このことをもっと簡単にいうと、「サラリーマンなんて割の悪いことやってられねえよ」とみんなが思うようになれば、日本的雇用は崩壊するのだ。
だれもが気づいているように、日本の労働環境にいま大きな変化が生じている。
ひとつはサラリーマンの側の変化で、各社が相次いで大規模なリストラに踏み切ったことで実数が減ったばかりか、賃上げの凍結やボーナス削減、社宅などの福利厚生の廃止、サービス残業に代表される無給労働の常態化で実質賃金が大きく低下した。
もうひとつの変化が、外資系企業の進出だ。彼らがグローバルスタンダードの雇用慣行を持ち込んだことで、サラリーマンにこれまでなかった転職のチャンスが生まれた。
日本企業はそもそも中途採用を受け入れないし、仮に入社できたとしても年功序列のキャリアラインから外れたところでゼロから再出発しなければならない。そうなると、なんらかの理由で会社を離れることになった有能な人材は、自分の知識や技能を市場価格で評価してくれる外資系を選ぶほかない。このようにして、MBAを取得して外資系企業に転職した後、コンサルタントやファンドマネージャーとして独立するのが90年代以降のビジネスキャリアのサクセスストーリーになった。一部のエリートサラリーマンは、外資系に転職すればもっと高い給料をもえらえるはずだ」と考えるようになったのだ(期待賃金が上がった)。
この状態を図示すると、下のようになる。
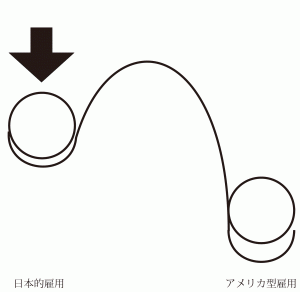
日本的雇用の側のボールが徐々に上昇し、山の頂点を越えたところで一気に反対側(アメリカ側雇用)に転がり落ちる。それを日本国は、法律による解雇規制や雇用助成金によって必死に押さえつけているのだ。
だがグローバル化した社会では、アメリカ型の雇用制度に明らかに優位性がある。日本社会で「雇用改革」が叫ばれるのに対し、アメリカの労働者は、どれほど失業率が高くなっても、かつてのサラリーマン(オーガニゼーションマン)に戻りたいなどとは考えない。終身雇用によって、同じ会社に一生涯拘束されることなど、彼らには想像だにできないのだ(これは、銃のない社会=日本と銃社会=アメリカの関係とちょうど逆だ。日本人は、どれほど犯罪率が高くなっても、個々人が銃によって武装する社会を選んだりしないだろう)。
日本的雇用からアメリカ型雇用への変化は不可逆的なもので、それを押しとどめる術はない。現在の制度を維持しようとすれば、失業率は際限なく上昇しつづけるだろう。好むと好まざるとにかかわらず、サラリーマンは絶滅する運命にあるのだ。
これはけっして絵空事の未来ではない。
「パパは何でも知っている」は50年代のアメリカ中流家庭を描いたホームドラマで、「パパ」は大きな保険会社のサラリーマン(アメリカでは組織人=オーガニゼーションマン)だった。60年代までは、アメリカでもひとつの会社で生涯を過ごす終身雇用が当たり前だった(親子孫3代が同じ会社で働くことも珍しくなかった)。それが70年代以降、日本メーカーをはじめとする外国企業との競争で業績が悪化すると、家族経営を信条としていたIBMやコダック、AT&Tなどの大企業が次々と大規模なリストラに追い込まれ、終身雇用や年功序列はまたたくまに消滅した。いまではすべての会社がいつでもどこでも交換可能な“汎用仕様”のマニュアルで運用され、労働者の価値観も変わり、自分たちが“サラリーマン”だった時代があったことすら覚えていない――わずか40年ほど前のことなのに。
慣れ親しんでいた日常が、ある日突然、まったく別の世界へと変わってしまう。それと同じことがいま、ぼくたちの世界で起きているのだ。
