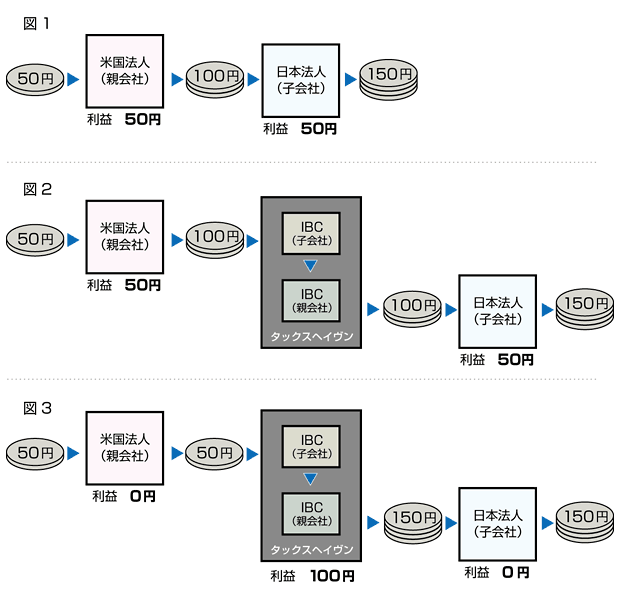矛盾に満ちた国際税務
経済のグローバル化が進むにつれて、国際取引は複雑の度を加えている。それに対して各国の税法は、二国間条約というきわめて旧式な道具でしか対応することができない。タックスヘイヴンは、この空隙から生まれた。
税の原則では、同一の所得に対して複数回の課税を行なってはならない。だが現実には、国際取引においてこうした二重課税は頻繁に発生する。課税権がそれぞれの主権国家の専権事項で、国によって居住者や所得の源泉の定義が異なるからだ。
次のような簡単な例で考えてみよう(図1)。
米国企業が50円で仕入れた商品を日本の子会社に100円で卸し、日本法人はそれを消費者に150円で販売した。この取引によって、米国法人と日本法人はそれぞれ50円の利益を得た(煩瑣になるので取引はすべて円建てで表記)。
ところが米国の税法では、法人は子会社を含む全世界の所得に対して納税義務がある。この場合米国は、日本での利益を含む100円の所得に課税することになる。
それに対して日本の税法では、本店・支店を問わず、日本で登記された法人を「居住者」と見なして課税する。そうなると米国法人は、日本の子会社の利益50 円に対して米国と日本で納税義務を負うことになる。こうした二重課税を放置すれば税負担によって利益の大半が失われ、米国企業は日本との取引を行なわなくなるだろう。
これでは税の公平性が毀損され、貿易や投資の意欲が著しく殺がれることになる。そこで日本と米国は租税条約を結び、相手国で支払った税額を納税額から差し引く(外国税額控除)ことで二重課税を排除している。
だがすぐにわかるように、この方式ではすべての国と租税条約を結ばなくてはならずきわめて効率が悪い(世界約200カ国のうち、日本が租税条約を締結して いるのは五六カ国)。そのうえ個々の租税条約が互いに整合性を持つとは限らないから、国際税務にはあちこちで矛盾が生じる。「国際租税回避」とは、こうした租税条約同士の歪みを利用して納税額を減らす技術のことだ。
ところがこのやっかいな問題は、タックスヘイヴンを利用することでずっと簡単に解決できる。
タックスヘイヴンの功罪
タックスヘイヴンで設立さ れる法人は、一般にIBC(International Business Company)と呼ばれる。この特別な法人は、国内でのビジネスを禁じられる代わりに、国外所得に対して法人所得税が課されない。そこで次に、IBCを 使って二重課税を回避する方法を考えてみよう。
タックスヘイヴンを利用すれば、米国法人はIBCの子会社をつくった り、IBCを本社とする日本法人を設立できる。そこで、米国法人が子会社であるIBCに商品を卸し、次いで、IBCを親会社とする日本法人がそれを販売し たとする。先ほどと同じく、米国法人も日本法人もこの取引で50円の利益を得る(図2)。
ところでこのケースでは、タックスヘイヴンはIBCに対する課税権を放棄しているから、米国法人とIBC、およびIBCと日本法人の間で二重課税は発生しない。米国法人、日本法人ともに、それぞれの国で50円の利益を申告納税すればいいだけだ。
このようにタックスヘイヴンは、国際間の複雑な取引をゼロベースに還元するというきわめて有用な機能を持っている。大航海時代にタックスヘイヴンが登場し たのは偶然ではない。租税条約を締結していない二国間の貿易は、香港やシンガポールのような自由港がなければ成立しなかった。国家の利害が衝突するなかで 国家を超えた世界市場を生み出そうとすれば、課税権を主張しない主権国家すなわちタックスヘイヴンは不可欠だった。
ところがここに、ひとつ大きな問題が生じる。
ふたたび先の例を挙げれば、米国法人は仕入れ価格と同じ50円でIBCに商品を卸し、日本法人は販売価格と同じ150円でIBCから商品を仕入れることも できる(図3)。契約自由の原則からはこの取引になんの問題もないが、差額の100円は無税のままIBCの利益となり、日本と米国は直接取引であれば得ら れたはずの税収を失ってしまう。この「節税」法はきわめて簡単かつ強力なため、放置しておけば国際取引から税金を得ることはできなくなる。
タックスヘイヴンは、その誕生からグローバルエコノミーに組み込まれていた。やがてそれは、課税権という国家主権の根幹を侵食していく。