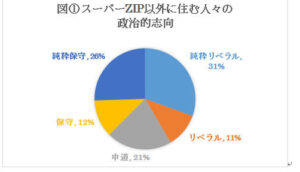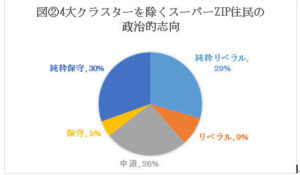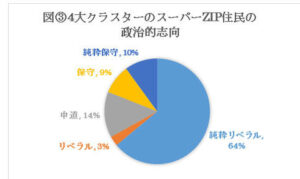ダイヤモンド社と共同で行なっていた「海外投資の歩き方」のサイトが終了し、過去記事が読めなくなったので、閲覧数の多いものや、時世に適ったものを随時、このブログで再掲載していくことにします。
今回は2020年9月1日公開の「「アメリカはディストピア、日本はユートピア」 経済格差の大きい欧米社会の驚くべき状況」です(一部改変)。
******************************************************************************************
新型コロナの影響を受けて、世界的に経済格差がさらに拡大するのではないかと危惧されている。アメリカ社会を揺るがしている一連の抗議行動も、黒人への「人種差別」に反対するだけではなく、その底流には自分たちの未来に対する不安や絶望があるのではないだろうか。
今回は、そんな「格差社会」を論じた本を紹介してみたい。
不平等が大きい国ほど社会問題が悪化する
2009年に刊行されたアメリカの経済学者リチャード・ウィルキンソンと疫学者ケイト・ピケットの共著『平等社会 経済成長に代わる、次の目標』(酒井泰介訳、 東洋経済新報社)は、経済格差の拡大がひとびとの健康、精神衛生、肥満、暴力、10代の出産、信頼などさまざまな指標を悪化させることを示して全英ベストセラーとなり、各国に翻訳されて大きな反響を呼んだ(日本語版は2010年刊)。続編である『格差は心を壊す 比較という呪縛』(川島睦保訳、東洋経済新報社)』では、それから10年後に世界の格差がどうなったのかを検証している。
ウィルキンソンとピケットは、所得格差の問題として以下の5つを挙げる。
1) 社会的な格差問題を悪化させる
2) 社会的な融合を阻害する
3) 社会的な団結を損なう
4) 地位への不安を高める
5) 消費主義や自己顕示的な消費を増大させる
これをひと言で要約するなら、「アメリカやイギリスのような経済格差の大きな国はなにもかもうまくいっていない」になるだろう。たしかに、新型コロナで露呈した「世界でもっとも経済格差の大きな国」アメリカ社会の矛盾と混乱は、「格差がすべてを悪化させる」という理論の正しさを証明しているように思える。
しかしその一方で、ウィルキンソンとピケットは「格差の小さな国はうまくいっている」として、北欧諸国や日本を例に挙げる。2人によれば、「アメリカはディストピア、日本はユートピア」なのだ。
ここで「ほんとうなのか」と疑問に感じるひとがいるだろう。戦後日本はずっと「アメリカのようになりたい」と努力してきたし(最近はちがうかもしれないが)、北欧と日本はまったく異なる社会だとされてきたからだ。
しかし、『格差は心を壊す』の冒頭に掲載された「不平等が大きい国ほど社会問題が悪化する」というグラフを見ると、たしかに所得の不平等と健康社会問題インデックス(平均寿命、信頼、精神障害(薬物・アルコール依存症を含む)、肥満、幼児死亡率、児童の算数・読み書き能力、刑務所収監率、殺人犯罪率、未成年出産、社会階層間移動などをベースに算出)はきれいに相関しており、所得の不平等がもっとも大きなアメリカの指標がとびぬけて悪く、所得の不平等がもっとも小さな日本の指標がいちばんいい。日本に近い国はスウェーデン、ノルウェー、フィンランドなど北欧諸国で、アメリカに近いのはポルトガルやイギリスだ。
これは、著者たちに都合のいいデータだけを選んだのではないだろうか。だが、所得格差の大きな国ほど暴力犯罪が多発し健康状態が悪化することは、1970年代以降、多くの査読付き専門誌に発表された研究論文で示されているという。
とはいえ、相関関係があるからといって因果関係があるとは限らない。「所得が不平等だから国民の健康状態が悪化する」のではなく、「不健康な国民が多いから所得が不平等になる」のではないだろうか。
しかしこれも、不平等と健康状態悪化のどちらが先行しているかを判断する一連の基準が開発され、それを踏まえた数百に及ぶ研究から、「所得の不平等拡大と様々な健康社会問題の悪化の間には確かな因果関係が存在する」ことが明らかになったとされる。
ウィルキンソンとピケットの「格差論」が広く受け入れられたのは、格差拡大が繁栄から取り残された貧困層だけの問題ではなく、富裕層を含む社会全体の問題だとしたからだ。
当然のことながら、多くの社会問題は富裕層より貧困層に深刻な影響を与える。しかし、「格差拡大で二極化が進む」ということは、「格差が拡大すれば富裕層はよりゆたかで幸福になれる」ということではない。富裕層(高い教育を受け、高給の仕事につくひとたち)であっても、格差の大きな社会では暴力犯罪に怯えて暮らすことになる。それよりも、格差の小さな安全な社会で人生を楽しんだ方がいいのではないか、との提案には説得力がある。
それに加えて本書では、所得格差がさまざまな社会問題だけでなく、心の問題を悪化させるメカニズムに注目している。欧米社会の驚くべき状況が報告されているので、すこし詳しく紹介してみたい。
80%の米国人が無力感、うつ、神経過敏、不安を訴えている
アメリカ人に対して、わたしたちは「積極的」「陽気」「おおらか」などのイメージをもっているが、ウィルキンソンとピケットによれば、これは虚像にすぎない。なぜなら、「米国人の80%以上がシャイ(shyness/臆病)に悩んでいる」のだから。
スタンンフォード・シャイネス・サーベイによると、「調査対象となった米国人の80%以上が、人生のある時点、つまり現在、過去、あるいは幼少期から現在までの全期間で、他人との接触にシャイだと答えている」。また3分の1以上が、これまでの人生の半分以上の期間でシャイ、約4分の1が自分を慢性的なシャイと見なし、いちどもシャイだと感じたことがない回答者はわずか7%だった。
10代の米国人(13~18歳)1万人以上を対象にした「全米併存疾患調査――思春期世代の調査」で、まったく初対面の同世代と出会ったときの反応を聞いたところ、ほぼ半数が尻込みしたと答えている。また60%以上の両親が、自分の子どもをシャイな性格だと回答した。
「パーティで他人と気楽に会話することができない」とか、「誰かが自分のことを噂していると考えただけで虫唾が走る」とか、さらには「スーパーのレジで店員相手に支払いすることさえパニックになる」「サングラスか帽子がないと出かけられない」というものまで、アメリカ社会で急速に「社交不安障害」が広がっている。
精神科で向精神薬を処方された患者数からみると、1980年以降、アメリカでは社交不安に苦しむひとが総人口の2%から12%に増えたという。訓練を受けた調査員が18~75歳の米国人1万人を対象にそれぞれの自宅で1時間の面談を行なったところ、「46%が過去に精神障害の症状、生活に支障をきたす深刻な経験をしたことがあると答えている」との調査結果もある。
米国心理学会の2017年調査によると、「80%の米国人が無力感、うつ、神経過敏、不安など複数のストレス症状を訴えている」とされ、ストレスの度合いを「1(全く感じない、あるいはほとんど感じない)」から「10(かなり深刻)」で自己診断させると、回答者の20%が8,9あるいは10の高レベルだと答えた。
世界保健機構(WHO)の調査では、「先進国では開発途上国よりも心の病の発症率が大幅に高い」ことが明らかになった。21世紀はじめに行なわれたWHOの調査では、精神障害の生涯発症率はアメリカ55%、ニュージーランド49%、オランダ43%、ドイツ33%に対して、ナイジェリアは20%、中国は18%だった。
メディアやSNSがうつを生み出す
生活水準はむかしよりずっとよくなっているはずなのに、なぜこんなことになるのか。ウィルキンソンとピケットは、格差が拡大する先進国では他人との比較を気にするようになり、それが社交不安やうつ病につながるのではないかという。
ボランティアの腕に水ぶくれの傷をつくってその回復状況を調べた実験では、人間関係が良好でない被験者ほど傷の治りが遅い。風邪のウイルスが含まれた鼻薬を複数のボランティアに投与した実験では、同じような環境で友だちが少ない被験者は、対照群に比べて風邪をひく可能性が4倍も高い。こうした実験から、「友だちが少なくなると健康状態が悪化する」ことがわかる。
これはヒトが徹底的に社会的な動物で、孤独=共同体から疎外されることが強いストレスになるからだろう。よく知られているように、ストレスは免疫や循環器系にさまざまな悪影響をもたらし、老化を加速させる。きわめて軽微なストレスでも、数カ月、数年も続けば、慢性疾患を引き起こし寿命が短くなることも示されている。
年齢とともに血圧が上昇するのは当たり前だと思うかもしれない。実際、先進国の調査対象者の血圧の平均値は60歳代が20歳代に比べて12~15ポイントも上回っていた。だが定住的な農業の経験のない部族社会、たとえばアマゾンの熱帯雨林で狩猟採集生活を送るシングー族やヤノマミ族では加齢による血圧の上昇は見られない。同様に、閉ざされた環境で生活するイタリアの修道女を20年にわたって観察した研究では、食事の内容は周辺地域のひとたちとまったく変わらないにもかかわらず、いくら年齢を重ねても血圧は上昇しなかった。
ストレスホルモンが急激に高まるのは「社会的評価(自尊心や社会的地位)」が脅威にさらされたときだ。他人が自分の行動に対してマイナス評価を下す可能性があるときは、そうでない場合に比べ、(ストレスホルモンである)コルチゾールの増加が3倍になる。
ウィルキンソンとピケットは、先進国でうつや不安症が蔓延するのは、メディアやSNSによって「身体的な魅力や知性、余暇の過ごし方、皮膚の色、芸術的な趣味、消費の傾向などすべてが、序列の評価の点で大きな社会的意味を持つようになる」からであり、経済格差がこうした差異を拡張するからだとする。その結果、不平等な社会では平等な社会に比べて心の病を持つ人が3倍も多くなるのだ。
社会的地位が低いほど心の病を抱えている
経済格差によって心の病が悪化するという主張には説得力があるが、「日本やドイツでは過去にどのような種類であれ心の病を経験した人は10人当たりで1人未満だったが、オーストラリアや英国では5人当たり1人以上、米国では4人当たり1人以上になっている」というデータはどうだろう。
日本でもうつは深刻な社会問題になっていて、「うつは日本の風土病」とまでいう精神科医もいる。それにもかかわらず、欧米では日本の倍以上もうつの患者がおり、経済格差の少ない日本は「精神的な健康度が高い国」に分類されている。これは実態を反映していないのではないだろうか。
じつはこうした疑問は著者たちも認めていて、「100万人の英国の生徒が精神的に病んでいる」「米国人の大人の25%以上が心の病を患っている」というデータに対して、ある精神科医から「医者としても市民の常識としても“ばかげて”いる」との批判が寄せられたという。「それは単に日常生活の“医療化”、すなわちちょっとした悩みや痛み、情緒不安定でもすぐに病気と見なして治療の対象としてしまう社会風潮を反映しているにすぎない」というのだ。
これに対してウィルキンソンとピケットは、世界保健機関(WHO)の世界メンタルヘルス調査とメンタルイルネス疫学調査にもとづいて、うつ病患者だけで世界で3.5億人もおり、とくに女性の病気としては、先進国・新興国を問わず、エイズ、結核を大きく引き離して第1位で、毎年100万人以上がうつ病で自ら生命を断っていることを指摘する。アメリカでも、18~30歳のいちばんの死亡原因は自殺なのだ。
ここから著者たちは、「精神科医が入念に調査された科学データの結果を信じることができなかったのは、心の病の発生率が想像を超えていたからだ」という。そればかりか、ひとは自分の苦しみを他人に知られたくないと思っているのだから、「心の病の広がりは実態よりも控えめにしか観察されないのではないだろうか」とすら述べる。先進国では、多かれ少なかれ、誰もがうつ病のリスクを抱えているのだ。
それでは、うつの分布はどうなっているのだろうか。2007年にイングランドで実施された心の病に関する総合調査によると、家計所得の最下位20%は最上位20%より“一般的な精神障害”になる可能性が高く、この傾向はとりわけ男性に顕著に現われる。「最下位の所得階層の男性は最上位の階層の男性と比較して、心の病を抱える(年齢を考慮した後の)確率は3倍も高い」のだ。
トランプは健康状態の悪い州地滑り的な大勝利をした
一般的な精神障害”のなかでももっとも極端な差が生じるのがうつ病で、「最下位階層の男性は最上位階層の男性に比べてうつ病にかかる確率は35倍も高い」。この傾向は家計所得が増えるにつれて改善していくが、全体を5つのグループに分けた場合、「(最富裕層の次に裕福な)第2富裕層」ですら、男性の場合、最上位層の男性に比べてうつ病にかかる確率はかなり高くなる。
フィブリノーゲンは血中の血液凝固因子で、ストレスに反応して増加し、傷を負ったときに血液の凝固を早め、多量の出血を防いでくれる。イギリス政府で働く中年の男女3300人を対象とした研究では、男女とも役職(地位)が下がるごとにフィブリノーゲンの量が増えていることが判明した。「序列の高いヒヒが目上のヒヒの攻撃を恐れるように、役職の低い役人もある種の攻撃に備えているように見える」のだ。
イギリスの心理学者ポール・グルバートは、絶望とは「抗議行動が成功しなかった場合の一種の“虚脱”戦略であり、ポジティブな感情や信頼の気持ち、探索や調査、追求の欲求は、身の安全のためにどこかでトーンダウンされなくてはならない」という。日常生活で敗北や挫折、いじめ、仲間はずれなどを経験することは誰にでもあるだろうが、それが長く続き、自分は孤立無援だと感じ、一人であれこれ悩む悪循環に陥ると、抑うつの深みにはまり込んで「ひきこもり」になる。
ひきこもりはこれまで、日本や東アジアに特有の社会現象だと考えられてきたが、欧米先進国でも珍しいものではなくなってきた(英語版Wikipediaにも“Hikikomori”の項目がある)。
それに加えて、欧米では子どもたちの自傷行為が大きな社会問題になっている。イングランドでは15歳の子どもの22%がこれまでに1回以上自傷行為を経験し、そのうち43%が月に1回の頻度だった。オーストラリアの調査では12人に1人(200万人)がある時期に自らを傷つけた経験があり、アメリカやカナダでは学齢期の子どもの13~24%に自傷の経験がある。
こうしたデータを列挙したあと、ウィルキンソンとピケットはうつのメカニズムを次のように分析する。
不平等が拡大すれば、社会に対する恐怖感や社会的地位への不安が高まる。その恐怖や不安が恥ずかしさの感覚を呼び、引きこもりや服従、従属の本能を強めていく。社会的な階層ピラミッドの背丈が高く、その傾斜も厳しく、社会に対する不信が強まれば、心理的な負担が増していく。社会的な地位を巡る競争や不信感が強まれば、人々は互いによそよそしくなり、思いやりの気持ちも少なくなる。すきがあれば他人を引きずり下ろそうとさえする。
2016年のアメリカ大統領選では、健康状態の悪い州でトランプが地滑り的な大勝利をした。「肥満、糖尿病、過度の飲酒、運動不足、短い平均寿命」を合体させた係数が、トランプの勝利をもっともよく予測したのだ。
こうしてウィルキンソンとピケットは、稀代のポピュリストであるドナルド・トランプ大統領を誕生させたのは、所得格差の拡大を放置してきたアメリカ社会だと結論する。
アメリカ社会は「二重経済」なのか
そのトランプ当選を受けて書かれたのがアメリカの経済史家ピーター・テミンの『なぜ中間層は没落したのか アメリカ二重経済のジレンマ』( 猪木武徳、栗林寛幸訳、慶応大学出版会)だ。大恐慌の経済史で知られるテミンはこの本で、アメリカ社会は「二重経済(double economy)」だと述べている。
経済学者のアーサー・ルイスは西インド諸島セントルシアに生まれ、イギリスで高等教育を受け、発展途上国の開発モデルによってノーベル経済学賞を受賞した初の黒人となった。
ルイスは、発展途上国には農村部と都市部の2つの経済部門があり、異なる発展水準、技術水準、需要のパターンによって分断されていると考えた。テミンはルイスのこの理論を援用し、世界でもっともゆたかなアメリカでも「二重経済」が生じており、それが原因で社会の分断が進んだと主張する。テミンによれば、アメリカはいまや発展途上国の様相を呈するようになったのだ。
ルイスの二重経済モデルでは、発展途上国には(都市の)「資本主義」部門と(農村の)「生存」部門があり、経済発展にともなって農村から都市へと労働力が移動する。労働力不足に悩む資本主義部門は、農民を住み慣れた故郷から引き離す必要があるため、生存部門の賃金を抑制する。こうして2つの経済部門の経済格差は、意図的(政策的)に拡大されるのだ。
これを受けてテミンは、アメリカ経済は「FTE部門」と「低賃金部門」の2つの経済に分断されているとする。FTEは「金融(Finance)」「技術(Technology)」「電子工学(Electronics)」であると同時に、「Full-Time Employee(フルタイム雇用)」でもあるという。具体的には、知識産業で働く高給の専門職のことだ。
一方の低賃金部門は、中西部のラストベルト(錆びついた地帯)にわずかに残った製造業のような衰退産業で、約50%が白人で、他の半分はアフリカ系アメリカ人とラテン系移民がほぼ同数だとされる。貧困というと黒人の問題と思われるが、黒人はアメリカ人口の15%未満で、仮に黒人の全員が低賃金部門で働いていたとしてもその5分の1に満たない。
アメリカの中間層は1970年に62%だったが、2014年には43%に減っている。中間層が解体して低所得部門が拡大した結果、貧困は白人(プアホワイト)の問題にもなったのだ。
「知能による分断」を無視しているのではないか
アメリカ人の30%が大学卒で、これがFTE部門に入る人数の上限となる。人口の20%がFTE部門とするならば、二極化によって80%が低賃金部門に追いやられる。
金融部門のCEOの年収は10億ドル以上、非金融部門のCEOは約1億ドルで、トップ1%の年収の下限は33万ドル、資産の下限は400万ドルだ(収入がトップ10%に入るアメリカ人の所得は10万ドル以上)。それに対して、中位の労働者の収入は約4万ドルとされる。
大学教授は専門職の典型とされ、中位の大学で教える教員(経済学)の年収は約10万ドルでFTE部門に属するが、英語・英文学の場合、年収は約6万ドルで、低賃金部門の中位労働者に危険なほど近い。
それにもかかわらず、インフレ調整済みの授業料は1980年から2012年にかけて主な州立大学で250%、全州立大学とカレッジで230%、コミュニティ・カレッジ(一般に2年生の公立カレッジ)で165%増加した。営利カレッジに入学するのは大学生の12%にすぎないが、彼らが学生ローン破産のほぼ半分を占める。学生ローンを抱える人は現在、4000万人を超え、ローンの総額は1兆2000億ドルを超えている。
これらはどれも重要な指摘だが、テミンの主張には疑問もある。アーサー・ルイスの理論では、発展途上国の「二重経済」は農村から都市への人口移動によって解消されることになるが、アメリカの「二重経済」では低賃金部門からFTE部門への労働者の移動は起こらず、逆に低賃金部門が増えていくだけだ(FTE部門は経済的には拡大するが、AIのようなテクノロジーによって大量の労働者は必要なくなっていく)。当然のことながら、農村から都市への移動が止まる「ルイスの転換点」も訪れないだろう。これほど大きく異なる社会現象を、同じ「二重経済」とすることができるだろうか。
アメリカ社会はなぜ「二重経済」になったのか。その原因についてテミンは、「黒人(マイノリティ)への優遇策を批判することで、白人労働者(マジョリティ)の賃金を抑制している」とか、「新ジム・クロウ法で黒人を大量投獄している」とか、白人が「多数派少数派majority minority(マイノリティ意識をもつようになったマジョリティ)」になったなどを挙げているが、これらはどれもすでにリベラルによる「グローバル資本主義=ネオリベ批判」の定番になっている。その結論が、「アメリカでは超富裕層のための政治が行なわれており、民主制から寡頭制に向かっている」では、正直、すこし拍子抜けだった。
なぜこのような中途半端な分析になるかというと、「二重経済」のもっとも大きな要因である「知能による分断」を無視しているからではないだろうか。
禁・無断転載